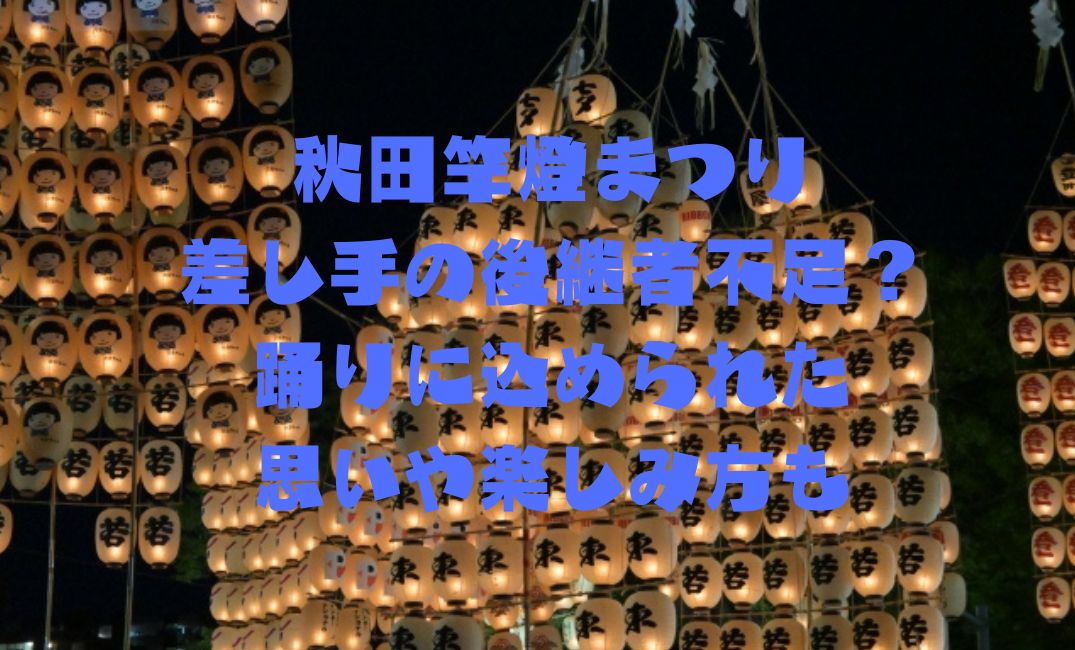毎年夏に秋田市で盛大に開催される竿燈(かんとう)まつり。
迫力満点の竿燈の妙技や幻想的な光景を楽しみにしている方も多いですよね。
でも、最近「差し手の後継者が足りない?」という声や、「この踊りにはどんな想いが込められている?」といった疑問も増えてきました。
今回は2025年の最新事情やエピソード、竿燈まつりならではの楽しみ方までたっぷりご紹介します!
今、竿燈まつりが抱える課題~差し手の後継者不足とは
竿燈まつりで豪快なパフォーマンスを披露する「差し手」。
その差し手が年々減少し、とくにここ数年、後継者不足が深刻になっています。

差し手の数が年々減少…。伝統の技術をつなぐ人が足りない町内もあるんです
差し手とは、12メートルにもなる大きな竿燈を手や肩、額、腰などで支える演技者のこと。
しかし少子高齢化や都市部への若者流出などで、地元に残る若い担い手が減り、ついには“差し手が確保できず今年は不参加に…”という町内も実際に出てきています。
いまや町内会や竿燈会では、地元小中高生への働きかけや体験会の実施、ベテランと若者の「合同チーム」結成など、まさに知恵を絞りながら後継者育成に力を注いでいるのが現状なんです。
後継者問題をどう乗り越える?地域の取り組み
伝統を守るため、秋田竿燈まつりでは様々なアイデアや努力が続けられています。

子ども体験や合同練習を通じて、“伝統のバトン”を次世代へ!
たとえば、地元の小中学生への差し手体験や、初心者向けの特訓教室、夏休みに開催される合同練習。
子どもたちが「竿燈の技や歴史」に触れる場をつくりながら、ベテランや地域の大人が丁寧に教えるなど、“伝統のバトン”をしっかり引き継ごうとしています。
また「差し手」以外にも、提灯づくりやお囃子手、衣装や用具の管理といった裏方の大人たちの協力もあって、まつり全体が守られているのもポイントです。
竿燈の踊りに込められた思い ― 祈りと誇りの伝統
竿燈まつりは、もともと厄払いと五穀豊穣、家内安全を祈る「ねぶり流し行事」が起源。
竿燈の形はたわわに実った稲穂そのもの。
秋田の人にとって米作りは命の根幹。「今年も豊作でありますように」「家族が健康で、災いがありませんように」という願いが踊りや技に込められています。

竿燈の揺れる光には、豊かな実りと家族の無事を願う気持ちが託されています
大勢の差し手が支える姿には「一人ではできない、みんなで力を合わせて生きていく」秋田らしい連帯感も。
実際の演技は見た目以上に難易度が高く、額や腰に竿燈を乗せて静止させる妙技は熟練の証です。
差し手や演者の本音「この祭りにかける想い」
差し手を何十年も続けるベテランや、初めて竿燈を手にした子どもたち。
それぞれの胸にあるのは「家族や地域の誇り」、そして「技を受け継ぎたい」「もっと多くの人に竿燈の魅力を知ってほしい」という純粋な気持ち。

竿燈を上げる瞬間は、どんな苦労も吹き飛ぶ達成感。地域みんなで盛り上がるのが最高!
妙技大会や夜本番のパフォーマンスは、大人だけでなく子どもたちも一生懸命。
「自分の町内の竿燈が一番!」と応援したり、演技後は一緒に写真を撮ったり、地域ぐるみで支え合いながら一夜を彩っています。
竿燈まつり2025 思いきり楽しむコツ
竿燈まつりでは、演技の美しさや迫力だけでなく、祭りならではの楽しみもたくさん!
- 間近で見る妙技
- 昼の妙技大会(エリアなかいちにぎわい広場)
- ふれあい竿燈
- 地元グルメや屋台

演技もグルメも夏の思い出!『触れる竿燈』『見る竿燈』どちらも楽しめるのが魅力です
まとめ ~どんな人にも開かれた「つなぐ祭り」でいよう
秋田竿燈まつりは、豪快な技や幻想的な明かりの美しさだけでなく、「人と人、世代と世代をつなぐ祭り」という側面も強く感じられる行事です。
差し手や裏方の努力で受け継がれる伝統、子どもから大人まで笑顔で支え合うコミュニティ…そのすべてが、夏の秋田をより元気にしてくれます。

伝統をつなぐのは、祭りを楽しむみんなの力!応援や参加で、竿燈まつりをもっと未来へ届けよう
2025年の竿燈まつりも、きっとさまざまな人たちの情熱と願いがあふれるはず。
観光として訪れる方も、ぜひ地域の人の思いや伝統の心にふれ、一緒に素敵な夏の思い出を作ってみてください。
※ 最新情報や地域の取り組み、イベントスケジュールは公式サイトやSNSでご確認の上、お出かけください